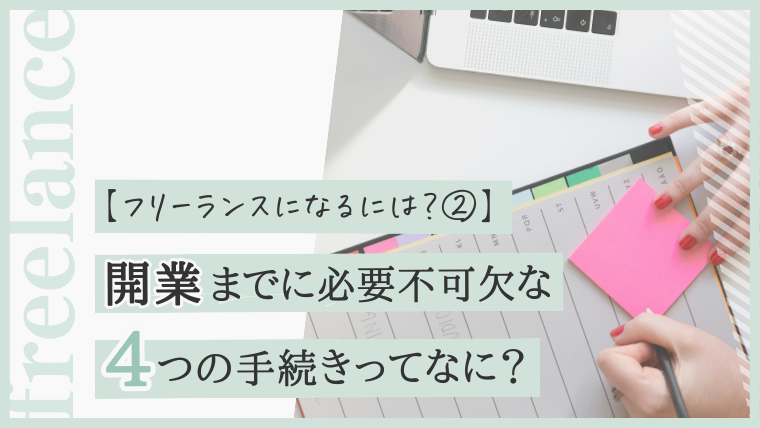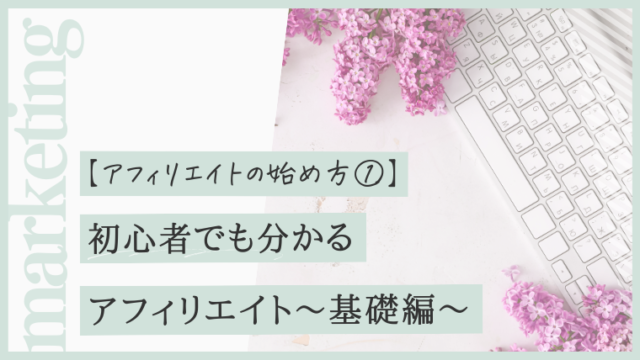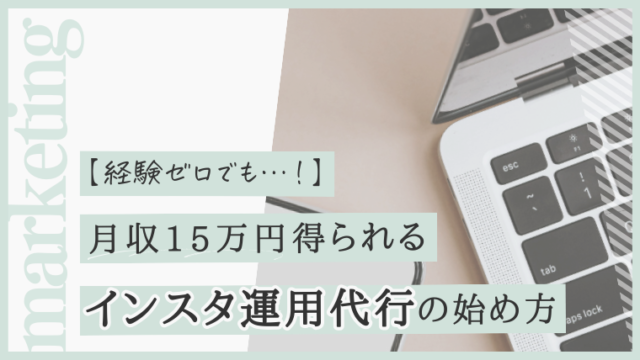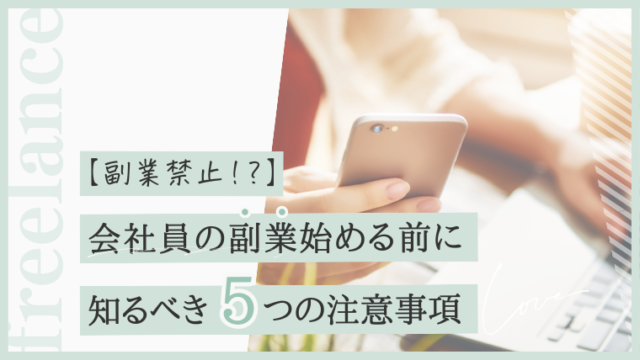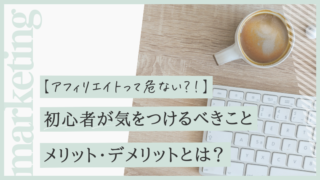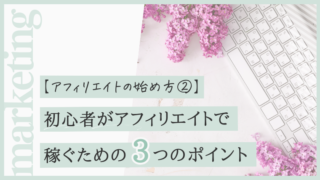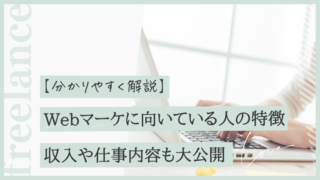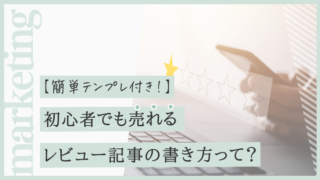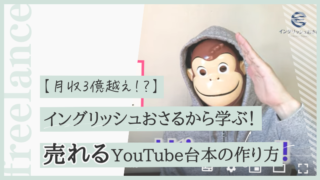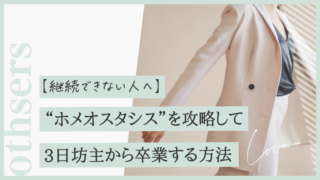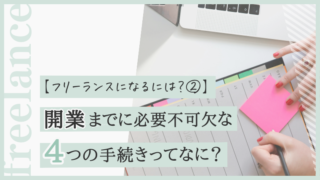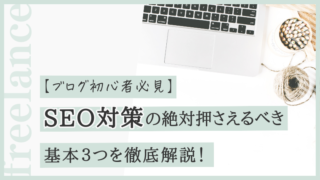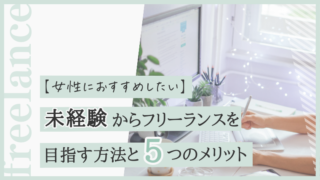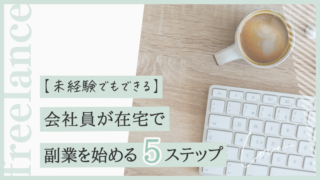こんにちは!Yukaです!
会社員を辞めて、フリーランスとして1からスタートしようと思うと、意外と色々な手続きが必要になります!!
これは知らなかった…では済まされない内容もあるため、最後までしっかりチェックしてください!
でも、まずはこの4つさえ手続きをしてしまえば、安心です!
会社員だと、会社が全てをやってくれていましたが、フリーランス、個人事業主として働き始めるには、開業届や保険、納税関連など自身でやるべきことがたくさん…
でもこれらのことって、誰も教えてくれません。
自分で調べてやっていくしかありません…
このような悩みがある方は、ぜひ読み進めてみてくださいね。
- フリーランスになりたいけど、どんな手続きが必要かわからない…
- 必須でやるべきことってなに…?
フリーランス!開業までにやるべき5つのこと
会社員を辞めて、フリーランスとして開業するまでの5ステップをご紹介します!
これから紹介する内容は、フリーランスとして働いていくためには、必須でやるべきことです。中には、退職後2週間以内に手続きをしなければならないものもあるので、必ずチェックしてくださいね。
- 開業届を提出する
- 青色申告を申請する
- 国民健康保険に加入する
- 国民年金へ切り替える
1┃開業届を提出する
フリーランスとして働く
=個人事業主になるということ。
会社を立ち上げなくとも、フリーランスで働くということは、一人一人が事業主というわけです。そのため、「開業届」の提出が必要です。この開業届を出すためにも、自分がどんなジャンルでどんな仕事をするのかをまずは、決めてみてください。
将来どんなキャリアプラン・ライフプランで過ごしていきたいか。しっかりビジョンを持つことで、自分がどのように行動していけばいいのかが見えてきます。
さて、開業するジャンルを決めたら、実際に「開業届」を提出する準備をしましょう。
開業したことを税務署に申告するための届出のこと。
基本的には、事業を開始して1ヶ月以内に税務署へ 提出するように定められています。
フリーランスが必ず開業届を出さないと罰則があったり、法令違反になったりするわけではありません。しかし、事業所得が一定額を超えると、開業届を出した方がいいです。
- 「屋号」を決めることができる
- 確定申告の際に、「青色申告」ができる
屋号を決めると、屋号つきの銀行口座を開設することができます。
事業を進める中で、収支の管理で出入金するのにも、屋号つきの銀行口座が1つあるととても便利です。
そして、このあと出てくる「青色申告」を受けることができるのも「開業届」を出すメリットと言えます。このために開業届の手続きをしている フリーランスがほとんどです。
「青色申告」ができると、税金の控除額が増えるので、しっかり手続きをしていきましょう。
詳しい開業届の出し方は、以下の投稿で詳しく説明しているので、ぜひチェックしてみてください!
2┃青色申告を申請する
開業届を出したら…次は青色申告の申請です!
また、「開業届」は、原則として開業日から1ヶ月以内に提出する必要があり、「青色申告承認申請書」は、原則として開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
控除を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出できないと、その年の確定申告は白色申告になってしまうので、注意が必要です。
定められた帳簿に記帳し、その記録に基づいて確定申告を行うこと。
また、青色申告ができる所得は決まっています!
| 青色申告ができる所得 | 不動産所得・事業所得・山林所得 |
|---|---|
| 青色申告ができない所得 | 給与所得・退職所得・譲渡所得・利子所得・配当所得・一時所得 雑所得 |
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
このように、青色申告の最大のメリットは「最大65万円の特別控除」が受けられるということ。しっかり申請方法を知り、進めていきましょう。また、その他にも赤字が生じた際、翌年度以降3年間繰り越すことができたりというメリットなどもあります。
■青色申告
:簡易簿記または複式簿記などの記帳方法が決まっており
特別控除として最大65万円の控除を受けることができる
■白色申告
:記帳方法が簡単だが、特別控除はうけることができない
青色申告と白色申告の違いやメリット・デメリットも把握して、選択できるようにしておきましょう。
3┃国民健康保険に加入する
会社を退職すると、これまで使っていた「健康保険証」の資格が無くなります。
フリーランスは、会社の件貢献を任意継続するなどの例外を除き、「国民健康保険」の加入が必要です。
日本は、全ての国民が何かしらの公的な医療保険に加入することが定められているんです。
会社員は、健康保険と厚生年金保険に加入していますが、フリーランスは基本的に地方自治体の健康保険に加入しなければいけません。
- 退職日の翌日から、14日以内
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 身分証明書(運転免許証、パスポート)
- 印鑑
- 離職票(退職時に会社から発行される) or 健康保険資格喪失症名称
or 退職証明書など退職日が確認することのできる書類
- 会社から退職したことを証明できる書類を受け取る
- 最寄りの役所の「保険業務担当窓口」で手続きを行う(郵送も可)
- 窓口、もしくは郵送で健康保険証を受け取り、完了!(発行まで数日から1週間程度)
4┃国民年金へ切り替える
フリーランスになったら、年金の切り替えが必要!
会社員の場合、「厚生年金」に加入していますが、フリーランスになると、「国民年金」に加入が必要となるため、切り替えの手続きをしなければなりません。
- 退職日の翌日から、14日以内
- 年金手帳
- 身分証明書(運転免許証、パスポート)
- 印鑑
- 離職票(退職時に会社から発行される) or 健康保険資格喪失症名称
or 退職証明書など退職日が確認することのできる書類
- 会社から退職したことを証明できる書類を受け取る
- 最寄りの役所の「国民年金窓口」で手続きを行う
- 自宅へ「国民年金保険料納付書」が届いたら…手続き完了!
原則、14日以内の手続きとなりますが、14日を過ぎてしまっても手続きは可能です。なるべく速やかに手続きを済ませるようにしてください。
フリーランスで+αでやっておくといいこと
ここまでは、フリーランスになるときに必要不可欠となる4つの手続きをお伝えしてきました。この4つの手続きさえ終わってしまえば、まずは一安心です。
意外と知らない、フリーランスになるなら+αでやっておくと良いことをご紹介します。
- 確定申告に向けて、クラウド会計ソフトを活用する
- 人脈、広告代わりにSNSを活用する
確定申告に向けて、クラウド会計ソフトを活用する
確定申告と言うと…日々の帳簿付けなど一人で頑張ろうと思うと、時間もかかってしまったり、申告ミスをしてしまったり、とても負担がかかります。
特に、前述した「青色申告」は正式な記帳が求められるので、とても時間がかかります。
だからと言って、税理士さんにお願いしようとすると5~10万円はコストがかかってしまいます。フリーランスになりたての1年目などは、収入が安定していない中、痛い出費ですよね…
そこでおすすめなのが、会計ソフトです!月額980円から利用することができます。日々コツコツと管理していくことができ、初心者でも分かりやすいく、おすすめです!!
人脈づくり・広告代わりにSNSを活用する
フリーランスは、自由に好きな仕事をできる分、仕事獲得も自分自身でやらなければなりません。
そこでおすすめなのがSNSでの発信です。
SNSは、ターゲットやペルソナに向けて有益情報を発信したり、自分のスキルや実績を伝えることができます。
しっかり運用し、ターゲットに刺さる発信をしながら、交流を深めることで、営業しなくても「あなたに頼みたい!」と営業しなくても自然と集客できる状態を作ることだってできるんです。
もちろん、簡単ではありませんが、やる価値は大!
同業者との繋がりができたり、そこから新たなお仕事に繋がることも…!
まずは、自分が何の専門家なのか、どのような経験や実績があり、どんな悩みを解決できるのかを伝えていきましょう。
おわりに
今回は、「フリーランス!開業までに必要不可欠な4つの手続き」についてご紹介しました!
- フリーランスになりたいけど、どんな手続きが必要なのか分からない。
- 必須で必要な手続きを知りたい。
こんな方もまずは、この4つの手続きさえ終えてしまえば、ひとまずは安心です。
会社員だと会社が全てやってくれていた手続き(納税や社会保険関連など)なので、「知らなかった!」「難しそう!」というものもあったかと思います。
しかし、期限内にやっておかないと、後悔することになるので、早めに対応できるよう準備を進めておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!